PMBOKガイド(日本語)が発売が予想とおり延期されました。
10月のPMIフォーラムでは直売コーナーも設置されてたので安心していたのですが甘かった。
まとめ買いしておけば良かった。
でもなんで延期のお知らせって、いつもお届け予定日の当日なんだろねー。
一般書店の店頭の方はというと、日本橋丸善、八重洲ブックセンター、渋谷紀ノ国屋には置いてありませんでした(10月末の情報)。
これら書店にないということは、たぶんどこもないんでしょうな。
さて、弊社では受講生にPMBOKガイドの販売も行ってます。
販売といっても別に再販して儲けようというのではなく「会社に受講料と一緒に請求したい」(会社の費用でチャッカリPMBOKガイドも手に入れちゃいたい)という受講生からのご要望に応えたサービスです。
なので、PMBOK第4版は既に何冊(何十冊?)も発注済みなのですが、決済が発送のタイミングなんだそうで、なんだか借金が増えていくみたいで、あまり気分いいものではありません。
これ会計的には「買掛金の増大」ですから、短期の運転資金が増える、すなわち短期のCF(キャッシュフロー)が改善されて悪いことではないのです。
ですが、資本が脆弱な中小企業がそんな指標を当てに経営をしてたら、キャッシュフロー経営、転じて自転車操業に陥るだけです。
ちなみに弊社では、実際の支払いは、できるだけ後払いや、一括支払いによって金利や割引の恩恵を受けながら、内部的には、支払いが確定的になった時点で、支払専用口座へ資金を移動させます。
こうすることによって、目にするのが、ネガティブな資金繰り情報となり、資金繰りに対する行動の遅れを回避できるようになります。
わざわざ資金繰表などは作らなくても、銀行が作成してくれる資料だけを追いかけておけば、大きな問題にはなりにくいわけです。
PMBOKでいうところのProactiveでしょうか。
【キャッシュフロー】
キャッシュフローはプロジェクトの優劣を判定する指標としてPMP試験にも登場する言葉です。
PMP試験では必ずしもその正確な意味までは問われませんが、常識的に収益・費用とは異なる概念であることぐらいは押さえておきましょう。
上記の例の利益計算ですが、
一人当たりの受講料を5万円とすれば、
+売上げ(受講料)5万円
-費用(PMBOKガイド)6千円
========================
利益(粗利)4万4000円
となります。
ではキャッシュフローはというと、
受講料は受領済みで、PMBOKガイドは後払いですから、
+売上げ(受講料) 5万円
-費用(PMBOKガイド) 6千円
+買掛金増加額(PMBOKガイド) 6千円
========================
キャッシュフロー 5万円
となります。
そんな、わざわざ足し引きせんでも、受講料5万円が入ってきて、PMBOKガイドの代金は払ってないんやからキャッシュフローもプラス5万ってすぐ分るやん。
と言いたくなるかも知れません。
そのとおりです。
その考え方を直接法といいます。
これに対して、上記のように未出分の費用と、未入分の売上の増減で逆算した方法が間接法です。
どちらのやり方でも結果は同じになりますが、実務でのキャッシュフローの計算はだいたい間接法によります。
理由は、間接法の方が簡単だから。
というよりも、直接法が煩雑だからと言ったほうがいいかもしれません。
組織の会計処理は通常、税法や商法、証券取引法に則っています。
これらは、発生主義といって、入出金のタイミングではなく、取引の発生に基づいて記録することになっています。
なので、キャッシュフローをリアルタイムで把握しようとすると二重の事務処理が必要になってしまいます。
(なので、やらない。)
ゆえに、ある時点(決算だとか、四半期だとか、月次)でキャッシュフローを把握しようとすると、間接法に拠らざるを得ないということです。
では、ここでPMP、ないしはPMP受験生に質問です。
Question
プロジェクトの評価の物差しは、なぜ会計的利益ではなくキャッシュフローになっているのでしょう?
キャッシュフローに関しては、まだまだ多くの論点があります。
折をみて書いていこうと思います。答えはそのときでも。
Copyright © BlissPointNetwork, © 小さな挿し木はするな All Rights Reserved.
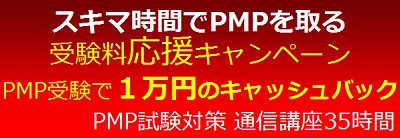
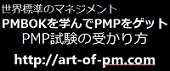
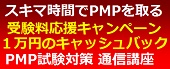
コメント